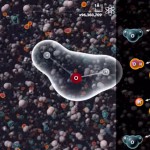2014年10月7日、2014年度のノーベル物理学賞に日本生まれの科学者3名が選出された。
赤崎勇、名城大学教授(85)。天野浩、名古屋大学教授(54)。中村修二、カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授(60)。
受賞理由は青色発光ダイオードの実用化。受賞者は皆、青色発光ダイオードの実用化において重要な役割を果たした人物だ。天野浩氏は名古屋大学教授だった赤崎勇氏の下で活動していた弟子に当たる人物で、中村修二氏は発光ダイオード生産において今では世界的なシェアを持つ日亜化学工業の研究員だった。
青色発光ダイオードの実用化にあたって三者はそれぞれ別々の技術開発で貢献しているが、青色発光ダイオードが発明され、実用化されるまでの過程を順を追って説明していきたい。
注目されなかった世界初の青色発光ダイオードの発明(赤崎氏)
青色発光ダイオードが製品として十分な性能を持って「実用化」されたのは1990年であるが、実は窒化ガリウム結晶によって作られた青色発光ダイオードは1970年台に赤崎勇氏によって最初に発明されている。ただ、実用に耐えうるものではなく、現在使われている青色発光ダイオードと比べると雲泥の差だが、当時としては革新的な発明だった。
にも関わらず世間の反応は芳しくなく、あまり注目されることはなかった。何故なら1970年代当時、青色発光ダイオードを発光させるための結晶に、窒化ガリウムの使うのは異端だと思われていたからだ。
発光ダイオードは半導体内部の電子の動きによって発光するが、光の色は電子が流れる半導体結晶の性質によって変わる。青色の光を出す半導体結晶として注目されていたのは窒化ガリウムとセレン化亜鉛だったが、窒化ガリウムによる青色発光ダイオードには非常に多くの難題が残されており、商用レベルには絶対になら無いだろうと思われていた。
つまり、青色発光ダイオードには窒化ガリウム版とセレン化亜鉛板が存在していて、世界のトレンドはセレン化亜鉛による青色発光ダイオードであり、窒化ガリウム版は売り物になら無いと思われていたのだ。
そのため、薄ぼんやりと青く光る窒化ガリウムの青色発光ダイオードは、せいぜいここまでが限界だろうと思われて見限られてしまった。それは赤崎氏が当時勤務していた松下電器も同じ考えであり、松下電器は窒化ガリウムによる発光ダイオードの商品化をこの時点で諦めてしまう。
それでも赤崎氏は諦めなかった。
「我一人荒野を行く」と語った赤崎氏は、それでも窒化ガリウム結晶による青色発光ダイオード開発に拘った。
そして10年の月日が経ち、大きな転機が訪れる。
「窒化アルミニウム・バッファ層」法の発見(赤崎氏・天野氏)
赤崎勇氏は名古屋大学に研究チームを移し、研究を続けていた。
そして、当時院生であった天野浩氏が赤崎氏の研究チームに加わることとなる。
松下電器での研究結果を活かし、赤崎氏は新たにMOVPE法と言う旧来の手法の良い点を活かし、悪い点を克服したような新たな結晶成長法を見つけ出す。しかし、それだけではより品質の高い窒化ガリウム結晶を生み出すことが出来なかった。
というのも、窒化ガリウムでの実用化が不可能だと思われていた理由の一つに、窒化ガリウム結晶を作るための「台座となる基板に最適なものが世界に存在しない」と言う理由があったからだ。言ってみれば、形の合わない凸凹な台座の上でジェンガをやるようなもの。多少は結晶を作れるかもしれないが、大きくて綺麗な結晶は作れず、十分に明るい青色の光を生むことは無いと思われていた。
そこで考えられたのが、窒化アルミニウムのバッファ層を台座となる基板と窒化ガリウム結晶の間に作ると言う手法。つまり、凸凹で形の合わない台座の上に平らな下敷きを置くと考えると分かりやすい。その下敷きの上でなら、今まで以上に綺麗な結晶を作れるのだ。