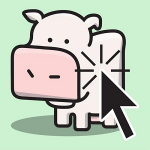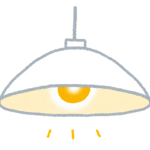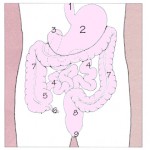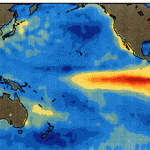佐世保で起きた女子高生によるバラバラ殺人。犯人の女生徒は、仲の良かった友人を絞殺し、死後に首や手を切断した事件。殺害の際、怨恨や金銭、口封じなどの明確な目的は無く、純粋に「殺害すること」が目的である快楽殺人であると見られている。
加害者の女生徒に関する報道は数多くあるが、事件の全貌は未だ明らかになっていない。
近年稀に見る未成年による非常に猟奇的な殺人事件ではあるが、過去にも同様の未成年の猟奇殺人は存在していた。世界的に治安の良いとされる日本で起きた未成年による猟奇殺人をここ20年前後でピックアップして、今回の事件と比較してみたい。